トップページ > YO's ROOM 後藤洋の吹奏楽の部屋
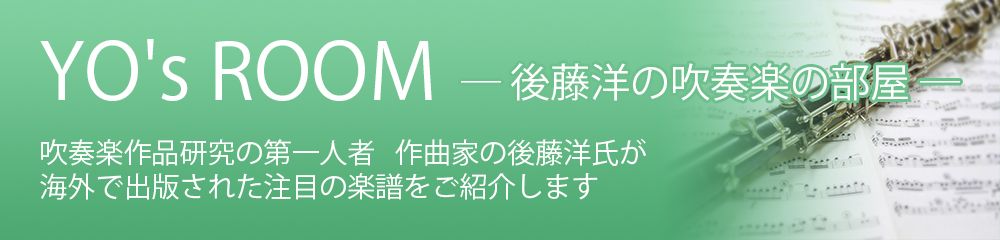
第5回に引き続き、ソロ楽器またはパートをフィーチャーしたレパートリーの特集です。今回は金管楽器と打楽器が主役になる曲をご紹介します。前回と同様、バンドのメンバーでもソリストになれる、やさしい曲ばかりですから、ぜひトライしてみてください。
今回は特別サービス(!)で、この秋に出版されたばかりの新譜も2曲ほど加えました。
マイケル・ストーリー編曲 A Saint-sational Trio! arr. Michael Story Grade 3 3:45 Belwin (Alfred)
まずは、トランペットが活躍する曲から。出版されたばかりの新しい楽譜で、日本では最も早いご紹介になります。おなじみの《聖者の行進》を、3本のトランペットをフィーチャーし、ディキシーランド・スウィングのスタイルでアレンジした1曲です。トランペットはそれほど難しくなく、音域も限られているので(最高音は実音F)、スタイルさえ理解すれば小学生や中学生でも無理なく演奏できるはず。もっとも、3人が同程度のレベルで演奏することはスクール・バンドでは簡単ではありません。したがって、2番、3番奏者を育てる機会としてこのような曲を活用するのもよいでしょう。
バンドの伴奏もやさしく効果的に書かれています。ソロとは別に伴奏にもトランペットが2パート含まれているのが難点なのですが、これはほとんど他の楽器と重なっていますから、場合によっては省略してもかまわないでしょう。30名程度から演奏可能です。
ヴィム・ラーゼロムス Trombonita Wim Laseroms Grade 3 4:45 Tierolff
前回もご紹介したオランダの出版社、ティエロルフから一昨年出版された楽譜です。この曲はトロンボーン・セクション(3パート)をフィーチャーした、賑やかなスウィング風の曲。ラーゼロムスはこの種のレパートリーの第一人者として定評ある作曲家ですが、さすがに効果的に作られています。コンサートで演奏すれば大喝采となるのは間違いないでしょう。
トロンボーンは付点リズム(スウィングなので実際には3連符)でかなり闊達に動き回るものの、スライディングがよく考えられているため、リズムが甘くならないように気をつけさえすれば、それほど演奏は困難ではありません。中学生、高校生がほとんど問題なくトライできるレベルです。ただ、このタイプの曲としては長いので、体力と集中力の持続がポイントとなるかも。バンドが単純な「伴奏」ではなく、トロンボーン・セクションと対等に渡り合うのも、この曲の大きな特徴です。
打楽器は、ドラム・セットの使用、または小太鼓、大太鼓、シンバルの分担、どちらでもできるように書かれています。編成は標準的ですが、アルト・サクソフォーンがほとんどクラリネットと重なっているため、クラリネットが不足でもあまり影響はないでしょう。
ヘンリー・フィルモア/ローラス・シッセル編曲 Lassus Trombone Henry Fillmore/ arr. Loras Schissel Grade 3 3: 00 Barnhouse
スーザ、キングと並び称される往年のアメリカの「マーチ王」、ヘンリー・フィルモア(1881-1956) は、自身トロンボーン奏者だったこともあって、トロンボーンを主役にしたバンドのための作品も16曲残しています。どれも吹奏楽の大切な財産と呼ぶにふさわしい、すばらしい作品なのですが、そのほとんどは初版の楽譜のままで、現代のバンドで演奏するにはいろいろと問題があり、改訂版の出版が待たれていました。そのような状況の中で、16曲中最もよく知られている、この《ラッサス・トロンボーン》(1915)が2000年にようやく復刻されました。編曲者のシッセルは20世紀のアメリカのマーチ研究における第1人者で、この楽譜はきわめて信頼度の高いものです。レパートリーに加えておくべき、スタンダードな1曲と言ってよいでしょう。
曲は気楽なラグタイムのスタイル。トロンボーンは3部に分かれているものの、多くの部分はユニゾンなので、何人で演奏してもよいでしょう。お得意のグリッサンドが存分に披露されます。バンドの編成は標準的なものですが、打楽器は3人か4人で演奏可能です。
ヘンリー・フィルモア/デイヴィッド・シェイファー編曲 Slim Trombone Henry Fillmore/ arr. David Shaffer Grade 3 2: 40 Barnhouse
ジーン・ミルフォード Tubasaurus Rex Gene Milford Grade 2 2:35 Carl Fischer
ジョー・バーク/ジェリー・ブルベイカー編曲 Tiptoe Through the Tubas Joe Burke/ arr. Jerry Brubaker Grade 3 3: 00 Belwin (Alfred)
原曲はジョー・バークが1926年に作曲し、1968年にタイニー・ティムによるリバイバルがヒットしたポップ・ソング《チューリップ畑をつま先でTiptoe Through the Tulips》。その歌を、テューバが活躍するようにアレンジしたのがこの曲です。スウィング風に始まり、その後ボサノヴァ、最後にはマーチ、と次々に音楽のスタイルが変化していくようになっています。
テューバはあまりソリスティックな扱いはされていないので、ひとりで吹くより、パート全員がステージ前方に出て演奏したほうがよいでしょう。低音木管楽器やトロンボーン、ユーフォニアムがテューバと重なる場面も多く、テューバだけでは心細い場合でも大丈夫です。
カール・ストロメン Tap Out Carl Strommen Grade 2 2:45 Carl Fischer
これは打楽器セクションが主役になる楽しい小品。打楽器は2台のスネア・ドラム、トムトム(3個)、ティンパニ、グロッケンシュピールという編成ですが、ふたつのスネアはほとんどヘッド(皮)ではなくリム(枠)を叩き、タップ・ダンスの靴音を模倣して掛け合いを行なう、という趣向です。したがって、太鼓を用意せず、机やステージの床を叩いてもかまいません。打楽器セクションの人数に余裕があれば、同一パートを複数のメンバーが担当し、バンドの前に「タップ・ダンサー」がずらりと並んで演奏するのも面白いでしょう(作曲者もそのように提案しています)。
打楽器セクションをフィーチャーしたやさしく楽しい曲は意外に少ないので、ぜひレパートリーに加えておきたい1曲です。
ルロイ・アンダーソン/ジョン・フォード編曲 Fiddle-Faddle Leroy Anderson/arr. John Ford Grade 2.5/2 2:45 Belwin (Alfred)
これも出版されたばかりの新譜です。セミ・クラシックの巨匠ルロイ・アンダーソン(1908-1975)の、1947年の作。オリジナルのオーケストラ版ではヴァイオリンがめまぐるしく動き回るこの曲、マリンバまたはシロフォン・ソロのレパートリーとしても親しまれており、実際ベルウィンから鍵盤打楽器のソロとバンドのための楽譜がすでに出版されています。でも、今回ご紹介するこの楽譜は、同じ曲の「グレード2」バージョン。マリンバ/シロフォン・ソロの難所は書き改められて音も適宜省略され、バンドの伴奏も平易になっているのですが、それでも原曲の闊達でおしゃれな雰囲気は変わりません。小・中学生でもトライできる楽しく効果的なコンサート・レパートリーです。楽器に余裕があれば何人かで一緒にソロ・パートを弾いても面白いですね。
コラム「レパートリーとは?」
この『後藤洋の吹奏楽の部屋』では、しばしば「レパートリー」という言葉を文中に使っています。おなじみの、でも、何となくわかったような、わからないような言葉ですね。
「レパートリー」の定義はどうなっているのでしょう? 辞書を開いてみましょう。
[repertoire]
①音楽、演芸などで、演者が演奏したり演じたりすることのできる曲目や芸の種類。上演種目。上演目録。
②その人の得意とする分野・範囲。
(三省堂 大辞林)
[repertory]
①=repertoire
②貯え。収積。
(研究社 新英和中辞典)
どうやら、「持ちネタ」に近い意味のようです。つまり、レパートリーとは演奏者(バンド)が常に演奏できるように準備している(あるいは準備しておくべき)楽曲のことなのです。「レパートリーに加えておくべき曲」とは、「演奏できるように準備しておくべき曲、または、演奏の機会を想定して楽譜を所有しておくべき曲」だとお考えください。「一度演奏して、あとはおしまい」という曲??そんな曲、たくさんありますね??は、「レパートリー」とは呼べません。日常の活動の中で度ある毎に演奏し、親しみ、親しまれる曲。それが「レパートリー」なのです。
後藤洋プロフィール

山形大学教育学部特別教科(音楽)教員養成課程卒業。東京音楽大学研究科(作曲)、ノース・テキサ
ス大学大学院修士課程(作曲および音楽教育)をそれぞれ修了。日本とアメリカの両国において、吹奏
楽と音楽教育の分野を中心に作曲・編曲家として活躍。海外で出版される吹奏楽作品の紹介、また音楽
教育としての吹奏楽の研究においても、日本における第一人者。自身が監修・編曲した『合奏の種』
『合奏の芽』(ブレーン株式会社)は、音楽表現の基礎を楽しく学ぶ新しいアイディアの教則曲集として大
きな反響を呼んだ。
2011年、ウインドアンサンブルのための《ソングズ》により、ABA(アメリカ吹奏楽指導者協会)スーザ
/オストワルド賞を受賞。また「ミッドウェスト・クリニック」(2006年および2010年、シカゴ)、世界シ
ンフォニック・バンド&アンサンブル協会(WASBE)世界大会(2009年、シンシナティ)等、多くの国際
的な講習会で講師を務め、いずれも高い評価を得ている。