トップページ > YO's ROOM 後藤洋の吹奏楽の部屋
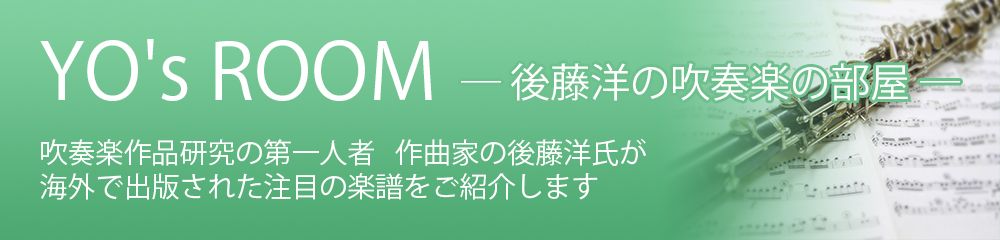
コンクールが一段落し、そして2学期も始まり、多くのバンドは新たな気分で活動を再開していることでしょう。
これから来年の春にかけては、さまざまな行事やコンサート活動に取り組みながら、バンドのメンバーひとりひとりの意識と技術をじっくり高める時期です。できれば、個々の奏者の力を伸ばし、しかもコンサートの聴衆に喜ばれる曲に取り組みたいですね。そこでおすすめしたいのが、特定の楽器を主役にしたコンサート・ピース。ソロやスタンド・プレイの経験は、今まで先輩の陰に隠れていた2年生や1年生を新しいリーダーとして自覚させ、技術と表現力を伸ばす上で非常に有効ですし、指導者の側も、ひとりひとりの音や奏法に目を向け、きめ細かい指導をするよい機会になります。それに、ソロやスタンド・プレイがある曲は聴衆にも喜ばれ、コンサート・プログラムの中で印象的なアクセントにもなります。特に、低音セクションをはじめとする、普段合奏の中で目立ちにくい楽器に光を当てることは、吹奏楽に対する一般の聴衆の方々の理解を深めていただく上でも重要でしょう。
このような「ソロとバンド」、あるいは「パートとバンド」のための曲はたくさん出版されていますが、大きく(1)プロや音大生レベルのソリストをゲストに迎えて演奏する作品、と(2)吹奏楽部員がソロまたはスタンド・プレイをする作品、に分かれます。今回は「個々のメンバーの力を伸ばす」という目的に従い、(2)のタイプの曲に絞ってご紹介することにしましょう。いずれも中学生、高校生でソロ・パートが演奏可能な作品です。なお、ご紹介したい曲が多いので、今回は木管楽器をフィーチャーした作品に限定することにしました。
エド・ハックビー The First Breath of Spring Ed Huckeby Grade 2 2:40 Barnhouse
まず、さまざまな楽器でソロができる曲をいくつかご紹介しましょう。これはハックビーが以前書いた自作の一部を編曲した、ソロ楽器とバンドのための穏やかな美しい曲。ソロは特定の楽器が指定されていません。旋律の音域と曲想からすると、フルート、アルト・サクソフォーン、トランペット、ユーフォニアムあたりが最も効果的なようですが、その他の楽器を主役にすることももちろん可能。クラリネット、バス・クラリネット、バリトン・サクソフォーン、バスーン、トロンボーンなどでも大丈夫です。
ソロは中学校1年生でも十分にトライできるレベルですから、1年生にかわるがわるソロを担当させてはいかがでしょうか? 伴奏はシンプルで非常にやさしいものの、ハーモニーがなかなかおしゃれです。適正なバランスのために、また演奏に加わらないメンバーが互いのソロを聴き合う意味でも、適宜伴奏の人数を減らして練習、演奏することをおすすめします。
ロバート・ロングフィールド編曲 Gabriel’s Oboe Ennio Morricone/ arr. Robert Longfield Grade 3 3:00 Hal Leonard
ローランド・ジョフィ監督、ロバート・デ・ニーロ主演のイギリス映画「ミッションThe Mission」(1986)の中で演奏される、非常に美しい音楽。この編曲は、ソロをオーボエ、フルート、クラリネット、トランペット、アルト・サクソフォーンのどれを使って演奏してもよいのが特徴で、明記されてはいませんが、オクターヴ下げてバスーン、バス・クラリネット、テナー/バリトン・サクソフォーン、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアムなどでも演奏可能です。タイトルが示しているとおり、本来はオーボエで演奏される旋律なので、この楽器を主役にした吹奏楽作品としては貴重なレパートリーになるでしょう。ソロのみならず、バンドの伴奏も大変美しく書かれています。
30人程度か、それ以下の人数での演奏がおすすめ。何人かで交替でソロを担当し、楽器紹介に活用することもできそうですね。
エンニオ&アンドレア・モリコーネ/ロバート・ロングフィールド編曲 Cinema Paradiso Ennio & Andrea Morricone/arr. Robert Longfield Grade 3 3:05 Hal Leonard
《ガブリエルのオーボエ》の続編として昨年出版されました。映画(1989年、ジュゼッペ・トルナトーレ監督)の中で奏でられたモリコーネの抒情的な旋律、という題材も、楽譜上のソロ楽器の設定(フルート、オーボエ、クラリネット、トランペットのいずれか)も、その他の楽器のソロの可能性も、前作と同じです。バンドのメンバーの意欲を高め、表現力を磨くうえで格好のレパートリーです。
デイヴィッド・シェイファー Flutopia David Shaffer Grade 2 (2.5) 2:20 FJH
ここから先は、特定のパートをフィーチャーした作品をご紹介します。これはフルート・セクションが主役となる、やさしく教育的な作品。この曲のフルートは3部に分かれていますが、いちばん上のパートをユニゾンで(場合によってはソロで)演奏しても、また1番&2番パートのデュエットにしてもよいようになっており、人数や実力に応じていろいろ融通できます。弾むような可愛らしい楽想が、スウィングになり、その後フルートのみのカデンツァ風の場面となるなど、音楽的なアイディアも多彩。しかも伴奏のバンドも非常に楽しく効果的に書かれています。「教育的」であることを忘れて楽しめる魅力的なコンサート・ピースと言えるでしょう。
楽譜どおりに演奏すると打楽器は6人以上必要ですが、トライアングルやタンブリンなどの小物は適宜省略してよいでしょう(シロフォンはいわば「第2の主役」なので省略不可)。バンド全体は20人程度いれば問題ありません。
ジャック・ブロック Those Fabulous Flutes Jack Bullock Grade 3 2:45 Belwin (Alfred)
こちらは少しグレードが上がります。フルート四重奏とバンドのための、スウィング・スタイルのおしゃれな小品。オプションでアルト・フルートとバス・フルートのパートも用意されています。フルートは、スタイルさえ理解すれば中学生でも演奏できるレベルで、ゲストを加えて演奏してもよいでしょう。また、バンドに含まれるピッコロ(第1フルートと重なっている部分が多い)をソリストに加えてもかまいません。4本のフルートはほぼ同じ技術的レベルが要求されており、それぞれ1本ずつソロをする場面もあります。
バンドの伴奏はきわめてシンプル。編成はほぼ標準的ですが、それほどたくさんの人数は必要ありません。打楽器はドラム・セット(何人かで分担してもよい)とグロッケンシュピールのみ。エレクトリック・ベースのパートがありますが、コントラバスでもOKです。
グレッグ・ダナー Clarinet Caprice Greg Danner Grade 2.5 3:15 C. Alan
クラリネット・セクションをフィーチャーした快活なポルカ/マーチ風の作品。クラリネットが活躍する同様の作品はほかにもありますが、この曲のように中学生でも無理なく演奏できるように配慮されたものはあまり多くはありません。スクール・バンドの貴重なレパートリーと言えるでしょう。本来、クラリネットはバンドの主役であるはずですが、最近はどのバンドでも主役の座を他の楽器に奪われがちです。ぜひクラリネットが活躍するこの種の曲を取り上げて奏者たちを発奮させ、また多くの人にこの楽器の魅力に目を向けていただく契機にしたいものです。
クラリネットはふたつのパートに分かれているものの、ほとんどユニゾンで動くようになっており、16分音符の動きはすべて音階。レジスター・キーを使った12度の跳躍も使われているので、練習のためのよい教材にもなります。
クラリネットが埋もれないように、バンドの伴奏は薄く、鳴りすぎないように書かれており、25人程度で演奏が可能です。
ハルム・エヴェルス Clarinetics Harm Evers Grade 3 4:25 Tierolff
ヘンリー・マンシーニ/ジョニー・ヴィンソン編曲 Pie in the Face Polka Henry Mancini/arr. Johnnie Vinson Grade 4 2:50 Hal Leonard
クラリネットをフィーチャーした作品をもうひとつ。ちょっとグレードは高いのですが、コンサートが盛り上がること必至の1曲です。1965年に制作されたアメリカのコメディー映画『グレートレース』(ブレイク・エドワーズ監督)の中で繰り広げられる「映画史上最大(!)のパイ投げ合戦」シーンで奏でられるポルカが原曲。《クラリネット・ポルカ》によく似たその曲想を生かしたアレンジが秀逸です。クラリネット・パートはソロでも、数人でもかまいませんが(そのため、いちおう伴奏パートにもクラリネットが含まれています)、コンサートではパート全員が前に出たほうが、視覚的にも効果が上がるでしょう。
ヴィム・ラーゼロムス Joyful Saxophone Wim Laseroms Grade 3 3:40 Scherzando (De Haske)
スティーヴン・ブラ Saxophonia Stephen Bulla Grade 3 2:30 Curnow Music
次回は金管楽器や打楽器をフィーチャーした曲をご紹介する予定です。お楽しみに!
後藤洋プロフィール

山形大学教育学部特別教科(音楽)教員養成課程卒業。東京音楽大学研究科(作曲)、ノース・テキサ
ス大学大学院修士課程(作曲および音楽教育)をそれぞれ修了。日本とアメリカの両国において、吹奏
楽と音楽教育の分野を中心に作曲・編曲家として活躍。海外で出版される吹奏楽作品の紹介、また音楽
教育としての吹奏楽の研究においても、日本における第一人者。自身が監修・編曲した『合奏の種』
『合奏の芽』(ブレーン株式会社)は、音楽表現の基礎を楽しく学ぶ新しいアイディアの教則曲集として大
きな反響を呼んだ。
2011年、ウインドアンサンブルのための《ソングズ》により、ABA(アメリカ吹奏楽指導者協会)スーザ
/オストワルド賞を受賞。また「ミッドウェスト・クリニック」(2006年および2010年、シカゴ)、世界シ
ンフォニック・バンド&アンサンブル協会(WASBE)世界大会(2009年、シンシナティ)等、多くの国際
的な講習会で講師を務め、いずれも高い評価を得ている。